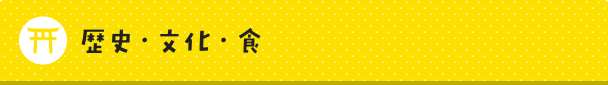宝塔的五輪塔 〜都城市〜(宮崎県都城市)
両塔とも高さ3メートルを超える。このような巨大なものは、都城盆地内では、正応寺跡地(安久町)の五輪塔と、この二基しか確認されていない。
この石塔については、慶長十九年(1614年)、高城(都城市高城町)が北郷領から本藩(薩摩藩)直轄領となり、高城城主であつた八代北郷忠相夫妻の墓が都城市の龍峯寺に改葬された際、長年忠相に恩恵を受けた高城の人々が忠相夫妻を慕って「詣墓(もうでばか)」として建てたという説がある。
火輪の軒端が垂直に切り落とされている形態は、古い五輪塔に見られる特徴であるが、軒の反り具合や相輪の装飾が省略されていることなどから、この石塔は、十七世紀のものと推測されている。
五輪塔は、下から
・方形(四角(六面体))の地輪
・円形(丸(球))の水輪
・三角(四角錐または三角錐)の火輪
・半月型(半丸(半球))の風輪
・団形(上の尖った丸(宝珠型)又は尖っていない団子型(団形))の空輪
からなり、仏教で言う地水火風空の五大(サンスクリット)を表すものとされるが、製作された時代・時期、用途によって形態が変化するのが特徴とされている。
人々は、古代より、宇宙(あらゆる世界)を構成しているとする地(ち)・水(すい)・火(か)・風(ふう)・空(くう)に感謝と敬意を表すことにより、歴史を紡いできたのかもしれないですね(^^)