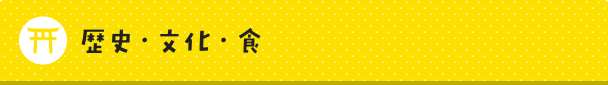天長寺の石仏群 〜都城市〜(宮崎県都城市)
薩摩藩の廃仏毀釈により仏教に関するものがほとんど失われたと言われるなか、完全な姿で残った貴重な石仏群である。
天長寺は、真言宗で松林山成就院と号し、江戸時代は、大乗院(鹿児島市稲荷町)の末寺であった。天文七年(1538年)八月、北郷忠相により祈願所として創建され、開山は、舜叡阿闍梨である。
『三国名勝図会』によると天文七年一月、忠相は、新納忠勝に奪われていた財部城(曽於市財部町)を財部寿福院快成と諮り、鶏鳴の合図をもって奪還に成功し、当寺を建立して快成の弟財部仏性院舜叡を開山としたという。
文禄四年(1595年)、北郷氏が祁答院(鹿児島県さつま町・薩摩川内市の一部)に転封されるに伴い、当寺も宮之城町(さつま町)に移転したが、慶長五年、北郷忠能の都城帰還とともに、現在地に戻った。
廃仏毀釈により、慶応三年(1867年)に廃寺となったが、現在は、再興されている。
現地には、地蔵菩薩立像、不動明王と両脇侍像、阿弥陀如来坐像、地蔵菩薩坐像も残っており、また、朱色の梵字が刻まれた碑もあり、歴史の深さを感じることができる。