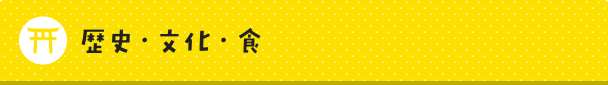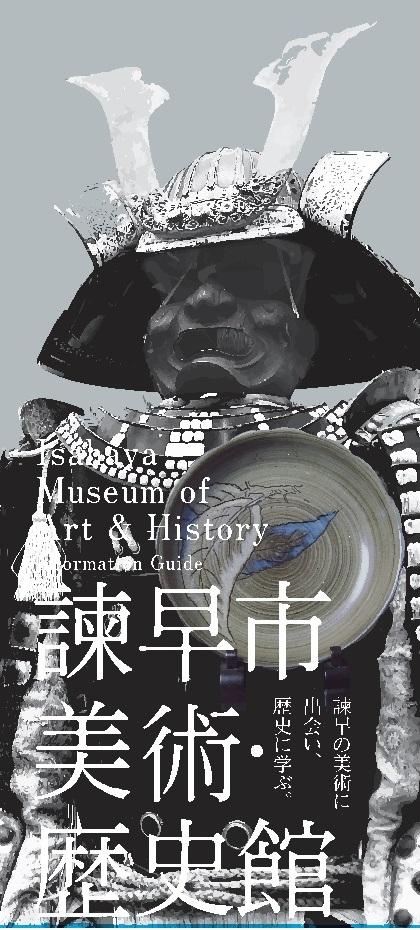「矢上八幡神社」と「八郎川」の由来(長崎県長崎市)
長崎の東部 諫早市との境に栄えたのが「矢上宿」
平安時代末期、弓の名手であった「源 八郎 為朝」が、この川にかかる橋の上から八幡神社にある大楠(距離約800m)を的に矢を射たという。
そこから、八郎川、八郎橋、八郎岳とついたといわれている。
この伝説の大楠が残るのが「矢上八幡神社」
石段の上にある2本の楠木の南側は最高幹囲5.3m、北側は10.15mと
県下有数の巨木(市指定天然記念物)
長崎街道と島原街道が合流する旧矢上村は佐賀鍋島藩の家老諌早氏の知行地で、長崎代官支配地と境界を接しており「番所」も置かれていた。