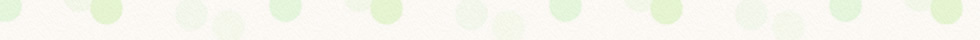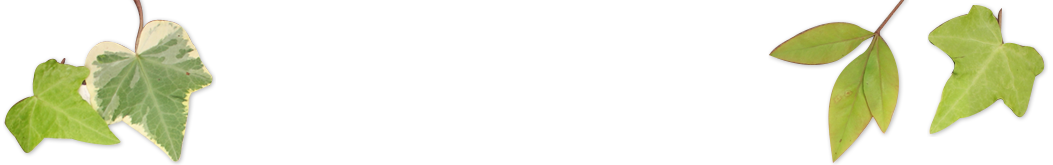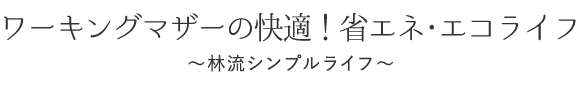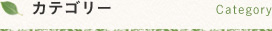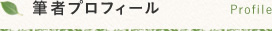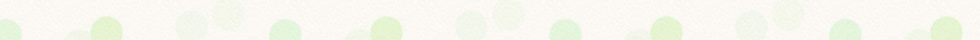障子の張替をしました。業者さんに頼もうとしたら、「破れないし省エネになりますよ」とプラスティック障子をすすめられたりして、結局、自分ですることに。
毎日見慣れているはずの障子なのに、知らなかった扉が開きます。
まずは雪見部分を外します。左に押し付けたら、すっと外れました。おー。
上げ下げする雪見障子が、好みの高さでピタッと留まる仕組みは、なんと竹で作られたバネでした。
しなって簡単に折れない竹は、バネとして使えるんですね。日本の伝統建築ってすごい!(近年は、ステンレスのバネに代替されてきているようですが。)
おまけでもらった化粧筆を刷毛代わりに、桟(さん)をたっぷり水で湿らせ、障子紙をはがす夜。伝統の知恵と技術の細やかさに感嘆するやら、唸るやら。
障子って、木と、竹と、紙と、米から作られた糊。全て、時を重ねて育まれた自然素材です。自然を生かす知恵に驚き、自然と共に生活していることの感慨が、しみじみ。
翌朝。乾いた桟(さん)を食卓に乗せて、新しい紙を貼ります。ここから手伝いに来てくれた友人に、五島うどんをふるまったりしながら作業。友人の家では子どもの頃、障子ごと川に投げ込んで、紙をはがしていたそう。なんてダイナミック!自然と一体化した営みですね。
午後から住宅の審査会の仕事があったので、大急ぎで紙を貼ったところ、あちこちシワが寄ってしまいましたが・・・シワには親近感がありますし、問題ない(笑)。
赤ちゃんが来るときは雪見障子を上げておけば、例の竹のバネが、見えないところでピタッと支えておいてくれます。破られたら、また張る楽しみができるというもの。
子供の頃、一家で大笑いしながらにぎやかに張替えをした、そんな思い出も懐かしく。
まっさらの障子に、気持ちも改まりました。日本建築っていいな。

写真左: 先人と対話しているような心温まる夜。たっぷり水で濡らしてしばらく置くと、一枚のまま、ぺらーっと剥がれます。
写真右:雪見障子の竹のバネ。これで、好みの高さにピタリ。
(2020年1月 林 真実)